Research list 研究一覧

- T. Sakabe, H. Okubo, T. Fujimoto, Y. Sonobe, Kusumoto
- 7th Asian South Pacific Association of Sport Psychology International Congress
本研究では、体育専攻学生における漸進的筋弛緩法(PMR)の実施初回の心理的効果についてPOMSを用いて検討することを目的とした。その結果、ストレス課題後からPMR後にかけて緊張、抑うつ、疲労、混乱の得点が有意に低下し、体育専攻学生においても初回からPMRの心理的効果を得られることが明らかとなった。
- H. Okubo, T. Sakabe, T. Fujimoto, Y. Sonobe, S. Tsuji, Y. Kusumoto
- 7th Asian South Pacific Association of Sport Psychology International Congress
本研究では、大学女子ハンドボール選手を対象にリラクセーション技法である自律訓練法(AT)と漸進的筋弛緩法(PR)を行い、初回の心理的効果について二次元気分尺度を用いて検討した。その結果、ストレス課題後にATもしくはPRを実施することで快適度が有意に上昇することが示され、両技法において初回から効果を得られることが明らかとなった。
- 大久保 瞳、生川岳人、山本沙貴、辻 昇一、松井幸嗣
- 日本ハンドボール学会第2回大会
本研究では、A大学に所属する女子ハンドボール選手を対象にPOMSを縦断的に測定し、競技成績との関連を思索することを目的とした。その結果、試合前の気分、感情が競技成績に影響を及ぼす一要因であることが示唆され、POMSは選手自身が心理面のコントロールを行うための一助となることが考えられた。
- 高井秀明
- 体育の科学,68,249-252,2018.
近年では急速な科学技術の発展により,利用する機器や装置の小型携帯化,利用の簡便化,価格の低下をもたらし,スポーツにおける科学技術の利用価値は今後さらに見出されることが予想される。特に,明確な評価基準を定めにくいスポーツ心理学領域では,科学技術の活用がまもなく重要な課題となり,スポーツ心理学の実践的アプローチに大きな変革をもたらすだろう。客観的データを基にしたスポーツ心理学の実践的アプローチができれば,アスリートやその指導者,さらには心理サポートスタッフ以外の医・科学スタッフとの連携の充実化が期待できる。
- 高井秀明
- 日本心理学会第81回大会発表論文集,2D-092,2017.
本研究では,日本人サッカー選手・指導者における異文化適応に必要な人的ネットワークの機能について検討した。その結果,異文化圏の日本人選手・指導者は,サッカー環境・状況に関する「情報の共有化」や日本とヨーロッパのサッカー選手・指導者の「人材交流」,さらにはサッカー先進国で必要な運動スキルの獲得を目指したアプローチについて検討する「強化プログラムの交流」を欲していることが明らかとなった。つまり,日本人選手・指導者がサッカー先進国で活躍するためには,上記の3つの内容を考慮した人的ネットワークを構築することが求められる。ただし,この人的ネットワークは,日本人のみで構成するのではなく,日本人の特長を活かすうえでも,異文化圏の選手・指導者を含める必要性があるだろう。
- 高井秀明、渡辺一志
- 日本体育学会第68回大会予稿集,119,2017.
本研究では,健常者と視覚障がい者が共に実施するアーチェリー教室への参加によるコミュニケーション・スキルと感情の変化について縦断的に検討した。調査対象者には,コミュニケーション・スキル尺度(藤本・大坊,2007)と一過性運動に伴う感情尺度(荒井・竹中・岡,1999)を全9回のアーチェリー教室の実施前後で回答させた。なお,アーチェリー教室は1回目から3回目を前期,4回目から6回目を中期,7回目から9回目を後期とした。その結果,コミュニケーション・スキル尺度の「自己統制」「自己主張」「他者受容」「関係調整」は,アーチェリー教室への継続的な参加に伴って高まる可能性を示した。また,一過性運動に伴う感情尺度の「否定的感情」は,前期・後期と比較して中期で高まる可能性を示した。それに対して,「高揚感」「落ち着き感」は,前期・後期と比較して中期で低下する可能性を示した。
- 高井秀明、柴原健太郎、本郷由貴、平山浩輔、藤本太陽
- 日本スポーツ心理学会第44回大会,302-303,2017.
本研究ではアーチェリーの試合時において継続的に心拍(心電図R-R間隔)を測定し,そこから自律神経活動の特徴を明らかにした。心拍変動の周波数解析における低周波(LF)帯域は,交感神経・副交感神経の両神経活動を反映しており,高周波(HF)帯域は副交感神経活動を反映している(Akselrod et al., 1985; Pagani et al., 1986)。また,LF/HFは交感神経活動を反映している。本研究における状態不安低群は,状態不安高群よりすべてのエンド(1エンドから6エンドまで)でLF nuの平均値が低く,HF nuの平均値が高かった。LF/HFの平均値をみると,1エンドから4エンドまでは状態不安高群が状態不安低群より高く,5エンドから6エンドまでは状態不安低群が状態不安高群より高かった。
- 柴原健太郎、深見将志、鈴木千寿、平山浩輔、高井秀明
- 日本体育大学紀要
本研究は、A大学のアーチェリー部に所属する大学生33名を対象に2種類のPower Poseの実施が気分に与える影響について明らかにすることを目的とした。その結果、High Power Poseの実施は気分状態を高めることが示された。また、Low Power Poseの実施は気分状態や覚醒水準を低下させることが示された。この結果から気分や感情はPower Poseの実施によりコントロールが可能であることが示された。
- 平山浩輔、高井秀明、坂部崇政、木原祐二
- 日本体育大学紀要
本研究は心理講習会において、実力発揮を阻害する問題に関する認知の歪みを同定し、適応的な認知の気づきへと繋げ、問題の改善へ向けた方向性の探索を目的とした。そのために、本研究では非機能的思考記録表を参考にして作成したセルフモニタリングシートを活用し、その効果検証を行った。対象者は23名であった。その結果、選手が抱えた多くの実力発揮を阻害する問題は、不安・緊張が高くても、実際には悪い結果が引き起こされる可能性は低かったことから、過度に不安・緊張を感じている選手が多いことが明らかにされた。
- 高井秀明
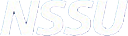
- 所属先
-
〒158-8508
東京都世田谷区深沢7-1-1
日本体育大学東京・世田谷キャンパス2415研究室 - 連絡先
-
高井秀明(Takai Hideaki)
日本体育大学体育学部体育学科
TEL:(03)5706-0863
FAX:(03)5706-0863
E-mail:takai@nittai.ac.jp



